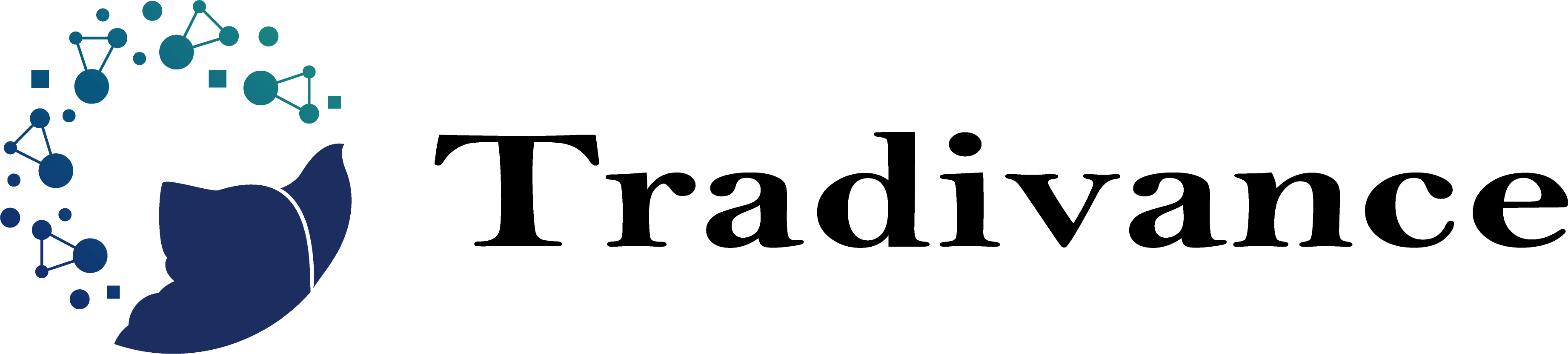本記事では、様々な企業でコンサルティング支援をさせていただいたり、DXの法人研修をさせていただくなかで、多くの場面で「ムダな会議」の話が出てきます。
実際に話を聞いてみると、確かに一見すると必要なさそうな会議やより効率的にできそうな会議が多いことに気づきます。
それは会議自体だけではなく、会議の前後で「資料準備」や「議事録作成」などにも多くの時間を取られている現場をよく目にします。
- 役職者が何名も参加して情報共有だけしている
- 会議の数は多いのに何も決まっていかない
- 社内用なのに議事録作成に何時間もかかって帰宅が遅くなる
そんなことある?と思う方もいるかもしれませんが、本当に多くの企業で相談いただきます。ご本人達も会議自体なのか会議の内容なのか、様々ですが「ムダ」であることは認識されているが、どうしていいか分からない、という御相談をいただきます。
そこで今回は、そもそも「ムダな会議」とは何なのか?どこに効率化余地があるのか?を考えてみたいと思います。
会議の効率化が重視されている理由
ITツールの発展と導入が大きな背景にあると考えています。
これまではオフラインで会って話すことが前提でした。確かに、それはそれで言語以外でも相手の状況が把握でき、丁寧にコミュニケーションをとることができてきました。
一方で、コロナ禍を経てオンライン会議ツールの普及やクラウド上での資料共有など、様々なツールが全国的に業務環境に導入されたと思います。
要はツール類や働き方の選択肢は、環境変化も合わさってかなり増加しました。一方で、会議の形態や頻度は慣例で変わり切らず、新しい選択肢に合わせて見直しをしきれていないというのが効率的な会議運営にいたっていない要因として大きいのではないでしょうか?
例えば、議事録を作成するのも音声の書き起こしツールがあります。
- PLAUD NOTE
- Clova Note(LINE)
- Teams
- ZOOM
- tldv
- taqticなど
もちろんアウトプットの品質は様々で、情報管理等にも配慮する必要があるのは分かります。では、全部の会議でこうしたツールが一切使えないかというとそういうわけではないでしょう。
Teamsの書き起こしをChatGPTを使って整理してもらうこともできます。
要は、新しいツールを使えるところから使っていく、不要な会議を定期的に見直す、そういう新しい環境やツールを目的に合わせて見直せていないことが「非効率な会議」が増えてしまい、会議を効率化したいという思いが強くなっている要因のように思います。
会議の無駄とは何か?

そもそも会議のムダとは何でしょうか?様々あると思いますが、主なところは次のような点があると言えるでしょう。
- 会議の目的が設定されていない/設定されていても合致していない
- 会議の目的が達成されない
- 相談しても検討が前に進まない
- 報告しても報告対象に抜け漏れがある
- よりコストの低い方法が分かっている(が取り入れられていない)
- アジェンダと関係ない人の参加
- 過剰な品質の資料作成や慣例で作っている議事録作成など
会議で非効率を感じる時を振返ると「目的があるかどうか」「目的があるが達成されていない」「よりコストの低い方法があるのに使われていない」というのが大きいように考えています。
会議も「相談したいのか、報告したいのか」によって取るべき時間も参加してほしい人も全然違います。
目的に応じて、誰に参加してもらうのか?誰が必要なのかを考えると分かりやすいでしょう。
ムダな会議がなぜ無くならないのか?
- 情報の報告だけされて解散する
- 慣例で定期参加する特に目的が無い会議
- ずっとしゃべっているが何も決まらないし、解決もしない
- なんとなく丁寧に作っている議事録
- ドキュメントやメモ書きでいいのに作成されるパワーポイント等
皆さんも会社で1度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
ではこうした時間がなぜ無くならないのでしょうか?多くの人は、こうした時間を有意義でない事は分かっており自分の時間を有意義に使いたいと思っていると思います。
「目的に照らした会議設計」と「振返りの時間」が無いことが大きいのではないでしょうか。
そもそも会議を設定する際に、「何をしたいのか」を明確にする時間を取っていることはあるでしょうか?その時間をめんどくさがって、なんとなく全員参加していればなんとなく情報共有もされている感が出ている会議が多いように思います。
また会議をやった後に、この会議の目的は何か?次回開催時に本当に同じ人が必要か?という振返りが行われていないことも多いでしょう。
最初はどうなるか分からない、参加者の反応や経験値も分からないので幅広に参加いただくこともあるでしょう。ただ、回を重ねる毎に必要な参加者もわかり、会議で議論したい論点も明確になっていきます。
その時に、きちんと振り返り、会議設計ができるかが大きなポイントのように思います。
特に歴史が長い企業では、毎年・毎月・毎週やっている定例会議の数が多く、結果的に参加者が「ムダだな」と感じる機会が増え、研修や業務効率化のタイミングで廃止や短縮候補の会議が数多く出てくる場面に出くわします。
ムダな会議の見直し方
会議を見直す時に大切なのは「目的は何か?目的は達成されているか?達成されていない場合、その理由はなぜか?」という3つの観点になるでしょう。
また会議自体の見直しと同時に、会議の前後で発生している作業も合わせて見直しましょう。

会議前の資料準備や論点整理、必要なら事前に少人数で一定の方向性を合意しておく等も有効です。会議後の議事録や情報共有のやり方も大きく見直せる部分があるかもしれません。
社内のMTGなのに定例会議で毎週のように議事作成に何時間もかけていたり、情報共有を部署毎に何通もメールで送付したりしていないでしょうか?(実際にコンサルティングや研修で聞かれるお話なんです)
こうしたムダを減らしていく、方法を改めて整理してみたいと思います。
1.会議記録の収集
多くの企業様ではTeamsやGoogleCalendarでスケジュールが管理されていると思います。その場合、1つ1つを目視・手作業で集めるのではなく、会議データを一覧で抽出してみましょう。
例えば、Teamsでは~~~をすることで会議データを抽出することは可能です。ただ、情報管理の観点からNGとなっている場合がありますので、システム部門等と確認しながら進めるのが良いでしょう。
2.会議目的と達成状況の確認
次に例えば1つの部で開催されている月間会議数と会議時間を可視化できたとします。その会議の目的を整理してみましょう。Excelやスプレッドシートで縦軸に会議名、横軸に開催頻度・開催時間・想定参加者数・会議目的・概要等で整理すると分かりやすいでしょう。
この一覧を見れば、まず時間がかかっている会議が分かります。時間も1回あたりの時間×開催回数×参加者数で定量化すると、合計でどの会議のコストが高く、見直しを検討したらよいかが分かるでしょう。
ここで忘れてはいけないのが「その会議の目的」です。
効率化をしている人の主観で「ムダがある」と言っているのではなく、会議の目的が達成されているかどうかで判断hしないといけません。仮にとても多くの時間がと人が関わっている会議があったとしても「その会議に必要な時間と人数」なら問題ないわけです。
特に社内から改革・効率化を図ろうとする時に、主観だけで進めてしまうことがありますが、そうした企画の進め方をすると早晩、社内で「本当にムダなのか?」「効率化する為の方便ではないのか?」という疑義をかけられてしまうこともあります。
客観性を失わない為にも会議の目的も合わせて整理するようにしましょう。
3.会議目的が達せられていない要因の確認
次に会議目的が達せられていない会議が「なぜ目的が達成できていないのか」を整理しましょう。
単純に「慣例で集まっているだけの情報共有会議」なのか「会議の中で直接話す必要がある時間がある」のかでも取るべき効率化施策が異なります。
また「完全にムダ」とするよりも丁寧に会議を主催している方や参加者の方とコミュニケーションを取って「必要な部分」を一部でも見つけてあげた方が、後々、社内でのハレーションも少なくなるでしょう。
こうして「ムダな会議が、どの程度ムダで、なぜ開催されているのか」が説明できるようになるでしょう。それからどの部分をどのように効率化するかという検討が始められると思います。
4.どれが必要な会議か?他に開催したほうがよい会議やアクションはないのか?
ここまで検討すると本当に必要な会議が何かも見えてくるでしょう。
- 実はオフラインで15分でも話しておいた方が良い
- 1週間単位で開催しているが間で報告だけしたほうが良い
- 意思決定だけ少人数で個別にやった方が良い(他の参加者は同席が必要なかった)
- 共有の場が無いので資料を保管していることを全体に共有したほうが良い
このように実は「やっておくと、より効率的にできる」「本当はこんなに人数をかけない方が良い」といったことが見えてきていると思います。
これは会議の目的が整理されているからこそ出てくる案だと思います。本来は何が必要なのかという観点は会社全体の業務効率を上げることにもつながるので、ぜひここまでをセットで議論・提案いただければと思います。
5.残った会議で効率化できることはないか?
残った会議で「何を効率化するのか」を検討していきます。
- 目的に対して人数が多い
- 目的に対して必要な準備ができていない
(意思決定の場なのに、判断できる情報が整理されてない等) - 目的に対して不必要に資料が作り込まれている
(社内共有の場なのに、リッチなパワーポイントが使われてる等)
(社内会議なのに議事録が逐語録のように細かく書かれている、展開に社内回覧と判子が必要等)
検討の際には【会議の前⇒会議中⇒会議後】とステップを分けると何がムダなのかが分かり、どう効率化したらいいかが検討しやすくなるでしょう。
会議関連業務を効率的に進めるツール
最後にありがちな会議を効率的に進めるツールをご紹介したいと思います。
事前準備|日程調整
まず社外との日程調整ツールはどんどん使った方が良いと思います。TimeRexやSpir等はカレンダーと連携して、空いている予定を選択するだけで会議を入れることができます。
ただ、社内で上位職者との会議調整は秘書さんを通して予定を確認しないといけなかったり、基本的に予定は完全に埋まっているので都度調整、なんてこともよくあります。そういう場合は、できることは限られてしまいます。
しかし、個人間の日程調整や比較的候補時間が取れる人同士の調整では、TimeRexやSpir等の調整ツールはとても便利になるでしょう。
更に、日程調整用のメールも署名にいれたり、専用GPTを作っておいて「宛先を入れたらメール文面案を作ってもらう」と言ったことも可能です。とにかくに同じ作業(会議候補日を探す、日程調整メールを作成するなど)を減らしていきましょう。
事前準備|論点整理や想定QA
誰に何を話すのか?どんな質問が想定されるか?そのためにどんな準備が必要か?
こうした問いの壁打ち合いとしてChatGPTやCopilot、Geminiは心強い相談相手になってくれるでしょう。会議の目的、参加者の役職や経歴を伝えると、何をどの順番で伝えたらよいか、どんな質問が想定されるかを回答してくれます。
これは生成AIの精度もさることながら、こうした時間を持つことで自分の会議の目的や設計を冷静に見つめなおすことができるようになり、より具体的な想定をもとに会議に臨めるようになるはずです。
自分を客観視するという意味でも非常に効果的だと思うので「資料を用意して終わり」ではなく、相手の立場に立って会議設計や資料内容を見直す時間を持つと、より効率的・効果的な会議時間にすることができると思います。
議事録の書き起こし&編集は生成AIツールに任せる
結構、TeamsやGoogleMeetに付帯する書き起こし機能の精度がいまいちなんですよね。他にもZOOMやRIMO等もいいのですが、そのまま使えるという感じではないでしょう(2025年現在)。
他にもGoogleDocumentやWordも書き起こし機能がありますが、やはり再編集が必要という段階だと思います。
PLAUD Note等はとても優秀だと思いますが、単価も高く、法人で導入となるとハードルも高いでしょう。
そこで、ZOOMやTeams等で一度書き起こしたテキストをChatGPT(学習させない設定)やClaude等を使って、再編集させるのが良いでしょう。社内会議の議事メモ程度であれば、この方法で合意事項とTodoに抜け漏れが無ければ十分だと思います。
クライアントMTGで経営意思決定にかかわるような内容だと情報管理だけでなく、様々な背景やステイクホルダーの意図、次のアクションに向けた整理などが必要になるので、人の手を介さないといけないと思いますが、全体の体裁はAIで細部の調整を人間が担う、ぐらいの分担で完成できるのではないでしょうか。
各種ツールの精度は日進月歩なので、今後はどんどん機械に任せられる場合が多くなっていくでしょう。
議論をその場で可視化・構造化するデジタルホワイトボードツール
オンライン会議自体はコロナ禍を経て、日本全体で導入が進んだ印象があります。一方で、オンライン会議での進め方は、企業によってさまざまなのではないでしょうか?
特にホワイトボードツールは、オンラインで共有しながら壁打ちや資料の完成イメージを共有するのに、とても有効でしょう。オフラインの会議でも「まだ意見が固まっていない」「どういう資料を作ろうか迷っている」という時にホワイトボードでイメージを共有できると、その後の手戻りが減ります。
オンラインのホワイトボードツールは付箋や画像も挿入でき、より直観的にわかりやすくまとめられるでしょう。
【ホワイトボードツールに備わっている機能】
- 文字やイラストを描く
- 図形や付箋、画像を挿入する
- 共同で編集する
- ホワイトボード画面を保存する
※ホワイトボードツールによって備わっている機能やUIは異なります。
会議を実施する時にホワイトボードツールを開き、参加者と共有して使います。
会議の内容は各参加者がホワイトボードツールを見ながら意見を言ったり、アイディアを書き込んで議論を深めることができます。
まとめ|無駄な会議の見直し方
会議の無駄を排除するためには、しっかりとした調査と分析が必要です。
時間がかかっている会議から「目的を見直して」みましょう。きっと目的と実態に乖離がある会議が見つかると思います。
そのうえで目的に必要な人数や参加者、準備や進め方、各種ツールを見直してみましょう。
特にAIツールの普及が盛んな昨今ですので、ツールばかりに目が行きがちですが「最も大きな効果を生み出す効率化は“やらないこと”」です。参加人数を減らす、もよいでしょう。
ツールありきではなく、目的に照らして何が必要なのかを整理してみてください。
効率的な議事録の取り方を採用し、AIツールを活用してリアルタイムでの記録や後のアクセスを容易にします。また、予定調整ツールを用いて、参加者全員のスケジュールに合った会議時間を効率的に決定することも有効です。これにより、会議の時間の無駄を減らすことができます。さらに、会議後は必ずアクションプランを決定し、それに基づいて各自が次のステップを明確にすることが必要です。このような方法を取り入れることで、会議から得られる成果を最大化し、企業全体の生産性の向上につなげることが可能です。効果的な会議運営を実現するためには、これらのポイントを組織内で共有し、実践に移すことが重要です。